 労務・年金
労務・年金 「令和3事務年度所得税及び消費税調査等の状況」より思うこと
毎年国税庁から所得税・消費税の税務調査等の実施状況が公表されます。事務所へ訪問して調査をする実地調査自体は回復傾向にあり、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先した結果コロナ禍前の水準に近づいてきているようです。今回はこちらの資料から気になった項目をピックアップして私見を書いてみたいと思います。
 労務・年金
労務・年金  年金相談
年金相談  ライフ
ライフ  年金相談
年金相談  年金相談
年金相談  年金相談
年金相談  労務・年金
労務・年金  年金相談
年金相談 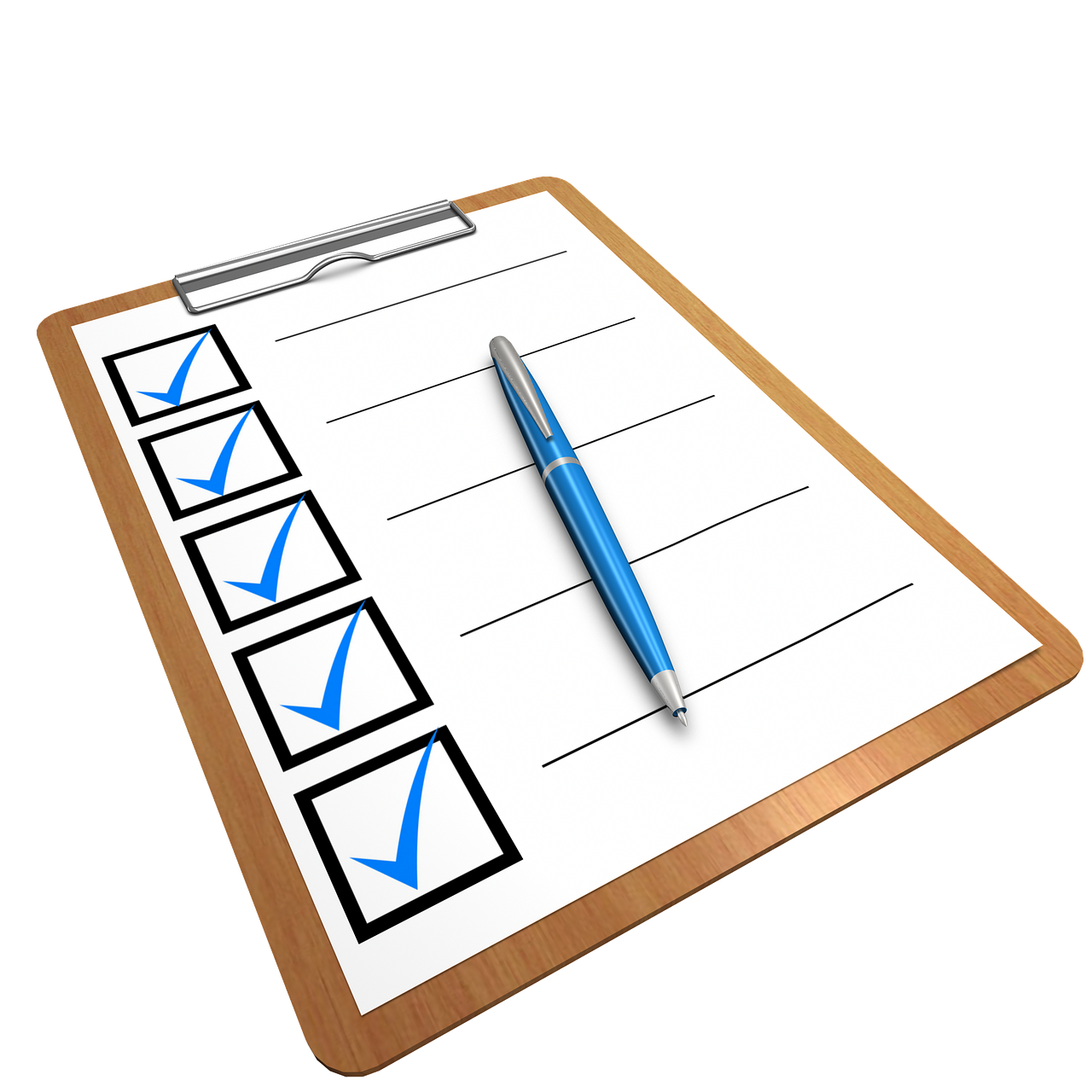 事務所運営
事務所運営  労務・年金
労務・年金