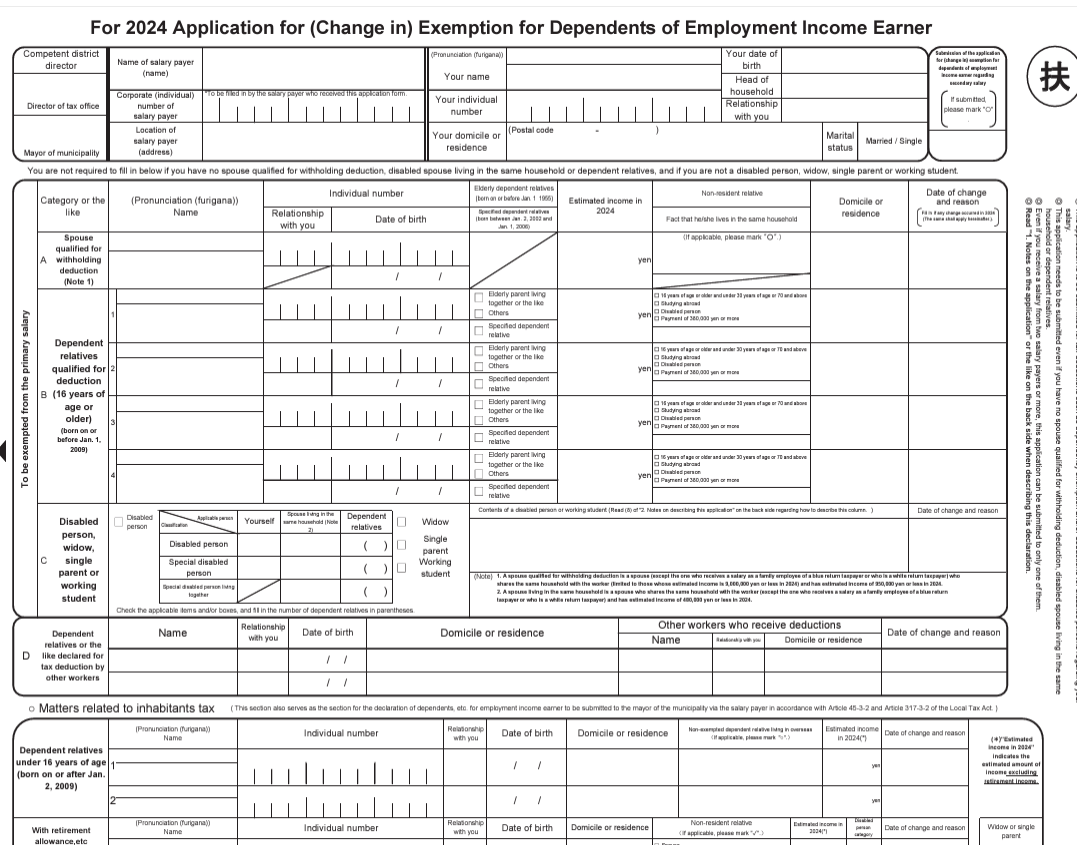12月12日です。
年末調整の対応をされている担当者の方にとって気を使う仕事ですけどしっかり対応をしたいものですね。
今日は年末調整について最近私が対応をした2つの事例をご紹介します。
翌月払の給与の年末調整
最初の事例です。
年末調整は、1年間で支払の確定した給与の総額について行います。
この「支払の確定した給与」は、以下の日で確定したとして判断をします。
- 契約や慣習で支給日が決められている場合:支給日
- 支給日が決められていない場合:支給を受けた日
したがって、給与規程で翌年1月10日に支給することになっている給与については、その支給日である翌年1月10日に確定することになります。
そのため、今年の年末調整の対象とはなりません。翌年分の年末調整の対象となります。
【事務所お知らせ】年内の給与を支給しない中途採用者の年末調整
では、次の事例です。
12月1日に採用をした中途採用者は、12月1日から31日までの勤務実績をもとに翌月10日に給与支給を行います。
そのため、年内に給与の支給はありません。
年末調整は給与の支払者である会社がその年最後の給与の支払いをする時に行うことになっています。
12月1日に採用した中途採用者に対しては、その年最後の給与の支払いを行っていませんので年末調整をすることができません。
したがって、従業員本人が自分で前職分の源泉徴収票をもとに確定申告を行うことにより税額の精算を行うことになります。
前職分の源泉徴収票は年末調整をしていませんので、給与総額とその給与から天引きされた源泉所得税額と社会保険料の金額しか記載されていません。
源泉所得税額は概算です。
扶養親族が異動になった状況や、生命保険料や地震保険料控除などは毎月の給与で天引きされる源泉所得税額には反映されていません。
そのため、前職分の源泉徴収票をもとに確定申告を行うことにより1年間の税額が正しいものになる、というイメージで大丈夫です。
確定申告に不安を感じる従業員がいたら…
2つ目の事例に関しては、中途採用者である従業員本人に確定申告をしていただくことになります。
その際、従業員から確定申告をしたことがなく不安だと相談されたらどう対応するのか。
その場合、会社内部で悩むことはせずに従業員にお住まいを管轄する税務署に相談に行くように勧めてみましょう。
確定申告期間は翌年2月16日から3月15日ですが、今回のような前職分の源泉徴収票のみで行う確定申告は納めた税金が還付になるケースが多いと思います。
還付申告については、翌年1月1日以降(実際は令和7年1月6日)なら提出をすることができます。
税務署への相談は事前予約が必要です。
まとめ
実際、この2つの事例は今年私が対応をしたものとほとんど同じです。
一瞬「年末調整するのか?」と考えましたが、結局は契約や規程により翌月払いであることが判明したので年末調整はしないという方向になりました。
中途採用者の方には確定申告が必要であることと、もし確定申告の仕方で不明な点があれば管轄の税務署に相談に行くようにお伝えしました。
参考になれば幸いです。
では。