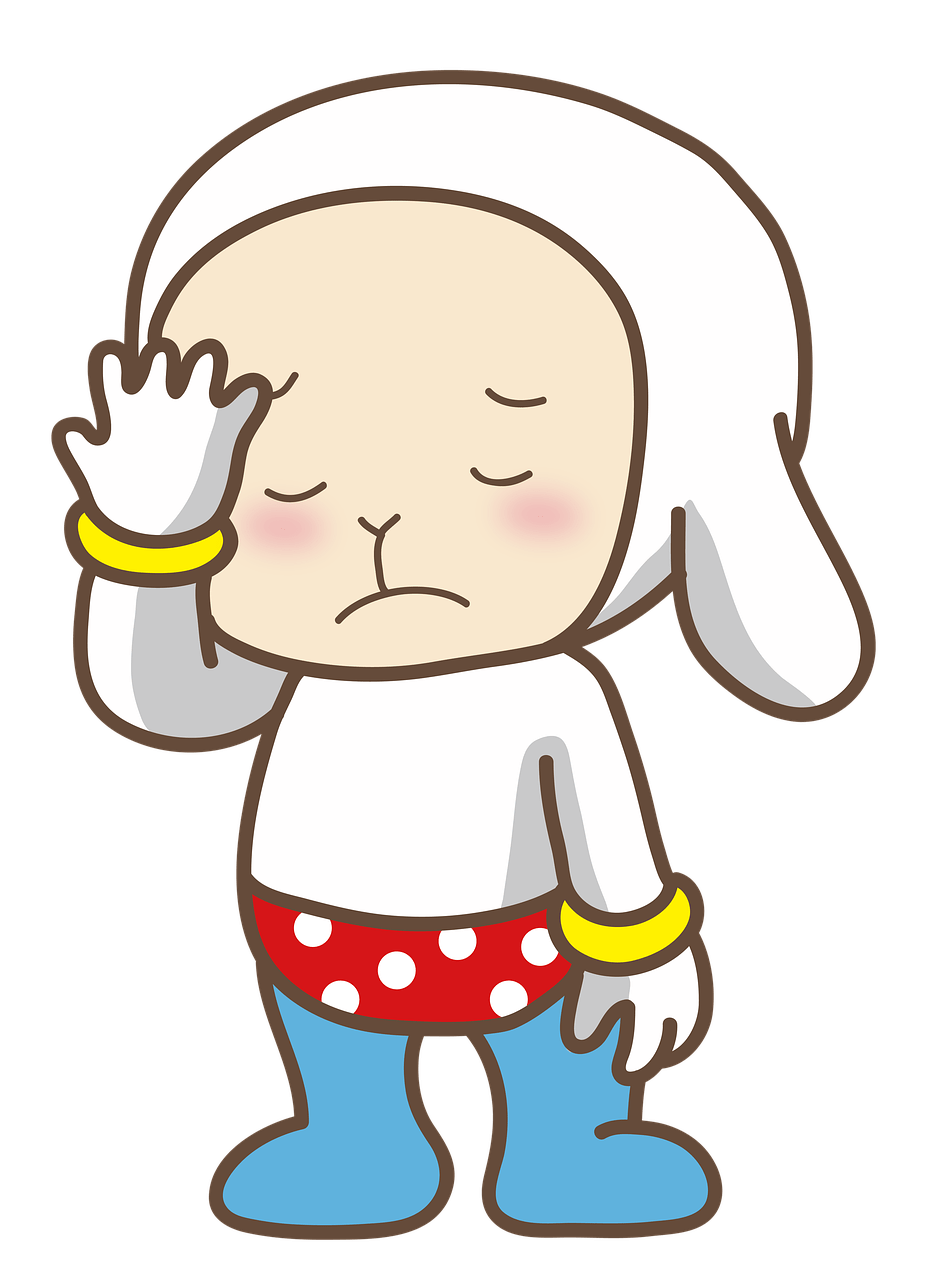来週の月曜日から確定申告期間に入ります。
所得税法そしてその所得をもとに計算をする住民税をもっと勉強しておけばよかったなと毎年思います。
税理士試験
私は税務職員でしたので、本来課税部門にいれば原則勤続年数23年以上で税理士試験が全科目免除され税理士登録ができます。
しかし、税理士試験の簿記論と財務諸表論に合格していたら勤続年数10年で税法科目が免除になることを知りました。
そのため、まずは簿記論と財務諸表論の受験を決意して5年かけて2科目合格しました。
法人課税部門の職員でしたので、税理士試験の法人税法や消費税法の勉強をすることにより実務でも役立つだろうと思っていたのですが、そこでうつ病を患います。
結局だらだらと勉強して体調がすぐれなくなり途中でドロップアウト…。
退職後まで酒税法と事業税以外の税理士試験講座は申し込んだものの講義を右から左に聞き流す程度にしかやっていませんでした。
【事務所お知らせ】年金相談員になって気づく
税理士と社労士登録を済ませてから、社労士業務で年金相談に従事するようになりました。
年金相談員として相談対応をしていますと、公的年金を受け取った場合に税金がかかるのかどうか確認を求められることがよくあります。
- 老齢年金は雑所得となり所得税と住民税がかかる
- 障害年金や遺族年金は非課税
- 雑所得っていうのは…
そんな会話の中から、所得税法と住民税をもっと勉強しておけばよかったな…と思ったわけです。
税務職員だった後半は法人課税部門の中にある源泉所得税の担当をしていましたので所得税法の一部分は何となくわかる程度。
しかし、確定申告となると分からない部分が多くて開業してから不安で仕方ありませんでした。
そして住民税。
住民税は税理士講座で勉強した記憶がうっすらあるくらいですが意外と相談を受けることがあります。
そもそも、所得をもとに住民税が計算されることを知らないお客様が多いのです。
年金相談から所得税や住民税の話題になることが多いことがわかり慌てたことを思い出します。
確定申告期「だけでなく」
税理士業務では法人より個人のお客様をメインとして活動するようになりました。
税務署から税理士会支部に依頼がある個人事業主の記帳指導を経験したことが大きいです。
そして顧問も個人事業主のお客様が中心になりました。
確定申告時期だけではなく年中所得税法や住民税に触れる機会があるため専門書や実務書・ネットを通じて確認する時間を持てています。
国民健康保険料や介護保険料も所得をもとに計算をしますから、結局所得の説明が必要になります。
税理士業務だけでなく社労士業務でも所得税や住民税に触れる機会が多くなりました。
税理士試験を受験していたら?
もし今税理士試験を受験するとしたら、きっと所得税法と住民税は受験しているかもしれませんね。
今やっている仕事に関連させたら、という意味ですけど…。
そういえば開業時にTACの実務講座で所得税法を勉強しましたね。
最近思うのはこの2科目について税理士講座を受講してしっかり腰を据えて勉強してみてもいいのかなと。
まあ専門書をしっかり読み込んで対応するほうがいいのかもしれませんけど、体系的な理解が必要だなと感じることがありますね。
まとめ
「所得税法と住民税の知識を使う機会ってどうせ確定申告時期だけじゃないか」と思っていました。
しかし、年金相談員の仕事をしていると毎回質問されるのです。
今行っている業務で必要な知識を身に着けていくことが私の課題になっています。
では。