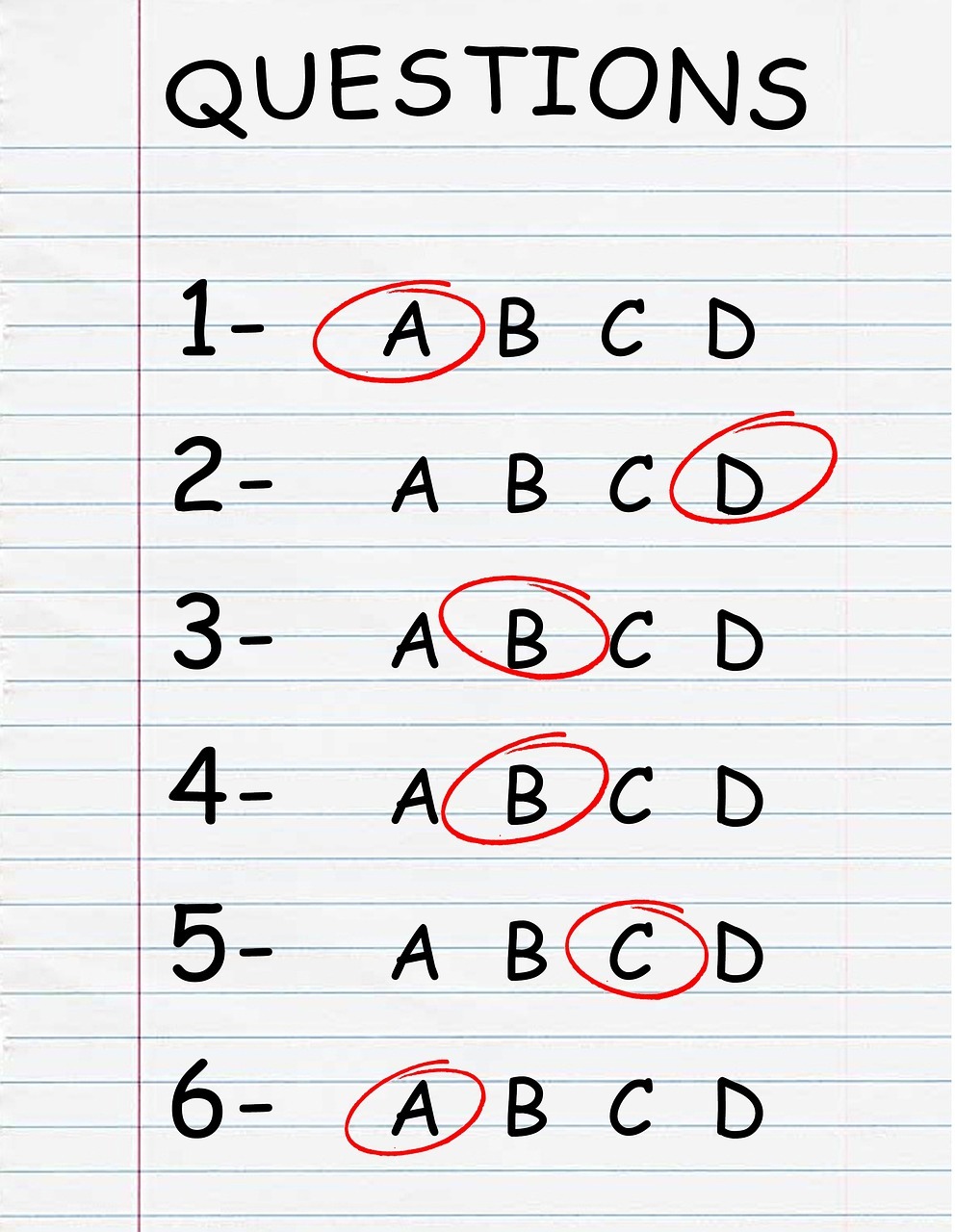年金相談員として契約をしている社労士は毎年3月末に年金相談の能力を確認するテストを受験しなければなりません。
そのため、毎年3月の確定申告が終わってから勉強をするようになりました。
「普段から相談対応しているのだからテストの点数はいいんでしょ?」と思われがちですけどそんなわけもなく…。
勉強が必要なワケ
年金相談能力確認テストは、穴埋め問題と択一問題があります。
穴埋め問題は一問につき3つか4つの空欄を埋めていくもので、1つでも間違っていると点数はありません。
択一問題は正しいまたは誤っているものを選ぶものです。
出題は年金制度全般に関するもので、老齢・障害・遺族の年金だったり法改正が絡むものまで多岐にわたります。
一番最初受けたときはほぼ回答できなかった記憶があります。
点数が低いと凹むんですよね。
やっぱりテストを受けるからにはいい点数を取りたいじゃないですか。
それを思ってから勉強を始めることにしました。
【事務所お知らせ】2か月年金相談を休んでいる
税理士としての確定申告業務がある関係で、2月・3月と年金相談をお休みさせていただいています。
そのため年金相談をする感覚がかなり鈍っているような気がしています。
お客様対応もそうですけど年金に関する知識そのものも忘れてしまっています。
また、年金相談をしていますと次から次へとお客様がお越しになられますのでじっくりと勉強をする時間が取れないんですよね。
年金相談の感覚を取り戻す意味でも能力確認テストを受ける意味があるなと最近思っています。
過去問⇔パンフレット・資料の繰り返し
ではどうやって勉強しているのかというと、過去問と年金相談時に持参しているパンフレットや資料の確認との繰り返しです。
令和4年3月からテストを受け始めていて、令和5年3月からは能力確認テストのほかテストではないですけどチェック問題が毎年1回配布されます。
なので今手元には計5回分の過去問がありますのでこれを一から解いていくわけです。
もちろん過去問ですから毎年法改正が行われている部分もありそこは飛ばしたりしますけどね。
解き始めるとまあ忘れているわけですよ…。
その際はパンフレットや資料を確認しながらチェックを進めていきます。
それだけを繰り返します。
1日1時間程度でしょうか。
勉強をするメリットとしてはやっぱり曖昧な記憶を定着させることにありますね。
一問一問改めてパンフレットや資料を読んで確認をすることにより中途半端だった知識を身に着けることができるのかなと。
意外と多いのは、去年意味が分からずに暗記で乗り越えていた問題が今年になり急に理解できるようになることです。
障害年金で多いような気がしますね。
腰を据えて勉強できる時間を
この能力確認テストの勉強をする意味で大きいのは、3月まで年金相談に入っていないことと確定申告期間が終わってからなので比較的時間があるんですね。
余裕があるからこそ4月からの年金相談に備えて知識を再確認できるツールとして能力確認テストを利用する、と決めてからさらに勉強がしやすくなりました。
まとめ
毎年テストが終わると点数がよくないので凹みます。
ただ復習をしっかりして不明点は先輩社労士に聞くなどして年金相談に入れるようにすればいいかなと割り切っています。
では。